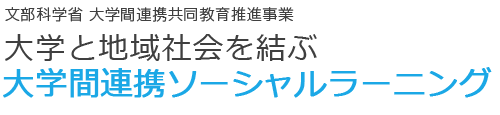
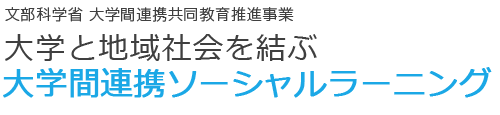
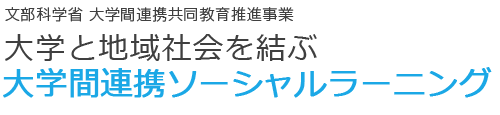
7月24日(水)から9月3日(火)まで全6回に渡り、「倉吉民踊(みんよう)の会」による「みつぼし踊り」を学生4名が学びました。
「みつぼし踊り」は、倉吉市を含む県中部、東伯郡で踊られてきた盆踊りで、天文(1532~1555)の頃から継承されており、昭和55年(1980)には、倉吉市指定無形民俗文化財に指定されました。みつぼし踊りには2つの踊りがあり、1つは古くから伝わる「伝統的なみつぼし踊り」、もう一方は、現在、倉吉市で夏に踊られている「行進型のみつぼし踊り」です。この行進型のみつぼし踊りは、昭和40年(1965)に郷土の踊りとして「みつぼし踊り」を復活させるため、倉吉文化財協会が調査を行い、誰もが覚えやすくすぐに踊れるものをとの要望に応えて考案されました。
今回学生たちは、主に「伝統的なみつぼし踊り」を講師からご指導いただき、講師の身振り手振りを見ながら、最初はぎこちなく動きながらも、回を重ねるに連れて徐々に振り付けを覚え形にしていきました。きれいな輪踊りにするためには、皆が呼吸を合わせなければならないことから、みつぼし踊りを通して周りに気を配るなど、改めて協調性について考えたという学生もいました。
また、みつぼし踊りの歴史を学ぶと共に、踊りの継承に尽力しておられる講師の想いに触れ、地域のつながりの希薄化や現代社会における次世代継承の難しさなどを課題として捉え、現代の社会的背景を考察しました。

△みつぼし踊り練習風景

△地域の方々とも一緒に練習しました

△シグナス祭(大学祭)でのステージ発表