教員コラム第6回@「音と人とのつながりを見つめて」(仙田真帆)
幼児教育保育学科にはさまざまな専門分野の専任教員がいます。それぞれの研究活動や授業内容について、リレー形式でコラムを掲載していきます!
今回は、幼児教育保育学科の仙田真帆助教です。仙田助教は、「教育学/音楽教育学」が専門で、専門科目「教育原理I」を中心に担当しています。
今回は、幼児教育保育学科の仙田真帆助教です。仙田助教は、「教育学/音楽教育学」が専門で、専門科目「教育原理I」を中心に担当しています。
教員コラム第6回
音と人とのつながりを見つめて
幼児教育保育学科
助教 仙田 真帆
(2024年12月16日掲載)
助教 仙田 真帆
(2024年12月16日掲載)
みなさん、こんにちは。今日は、私の研究についてすこしご紹介したいと思います。
私はふだん、音楽教育学分野の研究をしています。音楽教育学は、広く「人と音楽との関わり」を追求していく学問です。この大きな山に登る方法は研究者によって実にさまざまですが、私の主な研究手法は実験研究と呼ばれるものです。
音楽と実験って、何だか結びつきづらい言葉かも知れませんね。実験というと、白衣を着て、薬品を調合して…などといったイメージをもたれる方も多いのではないでしょうか。しかし、音楽教育学の分野では、この実験研究は決してめずらしいものではありません。
たとえば、近年の取り組みからいくつか例をご紹介します。
私はふだん、音楽教育学分野の研究をしています。音楽教育学は、広く「人と音楽との関わり」を追求していく学問です。この大きな山に登る方法は研究者によって実にさまざまですが、私の主な研究手法は実験研究と呼ばれるものです。
音楽と実験って、何だか結びつきづらい言葉かも知れませんね。実験というと、白衣を着て、薬品を調合して…などといったイメージをもたれる方も多いのではないでしょうか。しかし、音楽教育学の分野では、この実験研究は決してめずらしいものではありません。
たとえば、近年の取り組みからいくつか例をご紹介します。
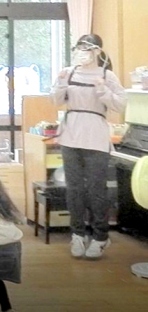
写真1
|

写真2
|
写真1は、音楽活動をする保育者は、活動中にどこを見ているのだろう? ピアノの鍵盤かな? こどもたちの顔かな? ということを、実際に眼球の動きを測定する機材を使って確かめようとした取り組みです。写真2は、音楽を聴くと、その後の集中力が高まるのかな?ということについて、反射神経を測定する機械を使って確かめようとした取り組みです。
こうした取り組みの種となっているのは、いずれも人と音とが織りなす営みを観察する中で生まれた、ほんのわずかな「問い」です。その問いを、さまざまなアイディアを使って実際に確かめてみるのが実験研究の醍醐味です。もちろん、計画や準備には膨大な時間がかかりますし、うまくいかないこともたくさんありますが、逆に、世の中の常識を覆すような結果がパッと明らかになることもあります。そんな時、目に見えないはずの音楽にすこしだけ近づけたようなワクワクした気持ちになります。
さて、写真1と2の結果はどうなったと思いますか? ぜひ、「問い」の答えを想像してみてくださいね。
こうした取り組みの種となっているのは、いずれも人と音とが織りなす営みを観察する中で生まれた、ほんのわずかな「問い」です。その問いを、さまざまなアイディアを使って実際に確かめてみるのが実験研究の醍醐味です。もちろん、計画や準備には膨大な時間がかかりますし、うまくいかないこともたくさんありますが、逆に、世の中の常識を覆すような結果がパッと明らかになることもあります。そんな時、目に見えないはずの音楽にすこしだけ近づけたようなワクワクした気持ちになります。
さて、写真1と2の結果はどうなったと思いますか? ぜひ、「問い」の答えを想像してみてくださいね。



