研究紀要 78号
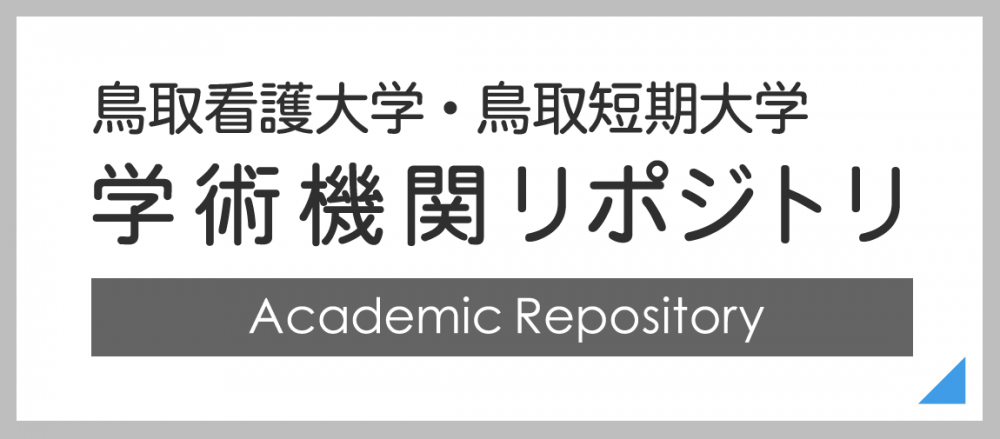
本学研究紀要は図書館本学関係資料コーナーに常設しております。
館外への持ち出しはできませんので、図書館内にてご利用ください。
第78号 2019年1月11日刊行 紀要一覧へ
| タイトル | 新設A看護大学の成人看護学実習を初めて受け入れる指導者の思い Thoughts of the Bedside Training Instructor in Charge of the Adult Nursing Clinical Practice in a New A College of Nursing for the First Time |
|---|---|
| 著作者 | 出石 幸子・永見 純子・村口 孝子・平野 裕美・前田 陽子 Sachiko IZUISHI,Junko NAGAMI,Takako MURAGUCHI,Hiromi HIRANO,Youko MAETA |
| ページ | 1-7 |
| 概要 | 本研究の目的は,A看護大学の成人看護学実習を初めて受け入れる指導者(以下,指導者)の思いを明らかにし,指導者との連携・協働における示唆を得ることである.実習病院の同意の得られた指導者6名にA看護大学の学生の実習指導をする上でどのような思いでいるのかについて,半構成的面接法を行い,質的帰納的方法で分析した. 指導者の思いとして【教員との連携・協働】【看護大学への役割期待】【指導者の指導観】【指導者の学生観】【指導上の困難感】【指導上の不安感】の6つのカテゴリーが抽出された.教員は,指導者の指導の視点と指導者の負の感情があることを理解し,相互に意見交換し,問題解決を図ることで,信頼関係を深めていくことが必要であり,教員が指導者と協働・連携を推進していくことは,教員と指導者の教育力向上につながることが示唆された. |
| キーワード | 新設看護大学 成人看護学実習 指導者 思い |
| タイトル | 2016年度の「出前・イベント型まちの保健室」に参加された住民の健康状態と意識に関する調査 The Survey of the Health Status and Conscious of the Participants for Delivery Local Health Room in Community Events and Community Centers in 2016 |
|---|---|
| 著作者 | 稲田 千明・松本 弘美・荒川 満枝 Chiaki INADA, Hiromi MATSUMOTO, Mitsue ARAKAWA |
| ページ | 9-14 |
| 概要 | 我々は「出前・イベント型まちの保健室」の参加者の健康状態とその健康意識や健康行動について明らかにし,この地域での「まちの保健室」のあり方の検討を行うことを目的として調査を行ってきた.2016年度の調査対象者は2015年度と比較して,男女比はほぼ同様で,年齢構成は若い層が減り60代の割合が多かった.身体データの比較では大きな変化がなく,目立った健康状態の悪化はみられなかった.体脂肪や収縮期血圧・拡張期血圧は年齢とともに増加しており,イベント種類ごとでは公民館の出前形式の参加者の血圧が他のイベントに比べて高かったことや,まちの保健室に参加することで「自分の健康状態が理解できた」「気軽に参加できいい機会であった」などの自由記述が得られたことは,2015年度と同様であった.さらに住民が健康を考えられ継続できるような対応が必要となる. |
| キーワード | まちの保健室 住民 健康意識 健康行動 |
| タイトル | 就労支援施設利用者のニーズに基づく地域社会生活定着度の困難性の検討 A Consideration of the Difficulties of the Retention Rate of Community Life on the Basis of the Employment Supporting Facility Users Needs |
|---|---|
| 著作者 | 中川 康江・荒川 満枝・木下 隆志 Yasue NAKAGAWA,Mitsue ARAKAWA,Takashi KINOSHITA |
| ページ | 15-18 |
| 概要 | 日本において精神疾患を有する患者の治療・療養は,長期入院治療に委ねてきた経緯が存在する.法的背景において,精神障害者の地域移行化はすすめられているが,2002年からの10年間において,退院後の家庭復帰者は減少傾向にあり,転院・院内転科者は維持したままである.障害者の地域移行を支えるために,精神疾患をもつ当事者にとっての就労は,退院後の地域移行先であり,拠りどころである.そこで,精神に障害を持つ当事者が地域での生活を定着させるため,就労支援事業所で就労に従事する当事者の意見を,調査・分析した. |
| キーワード | 就労支援事業所 地域生活への定着 当事者の意識 就労環境 偏見 |
| タイトル | 看護の人間学(2) ~「寄り添い」とブーバーの「我と汝」~ Anthropology of Nursing ~“Yorisoi”and Buber's “Ich und Du”~ |
|---|---|
| 著作者 | 荒井 優 Masaru ARAI |
| ページ | 19-28 |
| 概要 | 近年,多くの病院や福祉施設で,「寄り添う」看護の重要性が説かれている.「寄り添い」という言葉は非常にニュアンスに富む言葉であるが,それだけに曖昧さを含んでいる.看護において求められる「寄り添い」とはどのような対応なのか? ブーバーの「我と汝」論にもとづいて「寄り添い」について考える. |
| キーワード | 「寄り添い」 マルティン・ブーバー 「我―汝」 「我―それ」 「生命」 「共存在」 「対話」 キューブラー=ロス 「死ぬ瞬間」 |
| タイトル | 〈研究ノート〉 地域の自主防災の反省から見る看護大学への期待と活動可能性 Expectations and Possible Applications for a Nursing College from the Viewpoint of Regional Disaster Self-prevention |
|---|---|
| 著作者 | 藤井 麻帆・髙田 美子・美舩 智代・近田 敬子 Maho FUJII,Yoshiko TAKATA,Tomoyo MIFUNE,Keiko CHIKATA |
| ページ | 29-36 |
| 概要 | 2016年10月の鳥取県中部地震の前後に実施したK市の自主防災活動の担い手に対する調査結果に基づき,看護大学がどのような期待を寄せられ,また当該地域の中でどのような活動可能性があるのかについて考察した.自主防災活動との連携のためには,活動方法や可能性が互いに認識されることが必要である. |
| キーワード | 災害看護 地域 自主防災 連携 |
| タイトル | 〈研究ノート〉 母性看護学実習を多数の施設で実施する教育の課題 ~担当した教員の経験~ The Educational Issues in Maternal Nursing Practice at Many Different Fields |
|---|---|
| 著作者 | 前田 隆子・鈴立 恭子・井田 史子 Takako MAEDA・Kyoko SUZUTATE・Fumiko IDA |
| ページ | 37-41 |
| 概要 | 多数の施設で実施する教育の課題を明らかにするために,担当した教員の経験を調査し,今後の教育の示唆を得ることを目的とした.教員3名にグループインタビューして得られたデータを逐語録にし,質的分析した.結果:得られたカテゴリーは5であり,サブカテゴリーは13であった.『学びを促す指導と環境の中での良い実習体験』,『学生の乗り切る力』が見られた.他方『改善したい状況』,『学生にサポートの必要な状況』の臨床と協働して取り組む課題と『担当教員が取り組む課題』が明らかになった. |
| キーワード | 臨地実習 母性看護学 多施設 教員の体験 |
| タイトル | 〈資料〉 鳥取短期大学司書課程の現状と受講生の意識調査 A Survey on Students' Condition and the Current Status of Librarian Training Courses at Tottori College |
|---|---|
| 著作者 | 長岡 絵里佳・西尾 肇 Erika NAGAOKA, Hajime NISHIO |
| ページ | 43-52 |
| 概要 | 鳥取短期大学司書課程の充実・発展をめざし,司書課程の現状を整理し,受講生の意識調査を行った.1年生に対する本や読書についての意識調査によって,本好きな学生たちの読書傾向が把握でき,全受講生対象の意識調査では,資格を取得する理由や図書館,司書のイメージが明らかになった. |
| キーワード | 司書 学生 意識調査 読書 書店 図書館 |
お問い合わせ先
鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館
所在地:〒682-8555 鳥取県倉吉市福庭854
TEL:0858-26-9121(本館)、0858-27-2809(別館)
E-mail:library@cygnus.ac.jp



