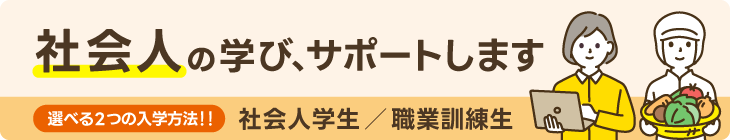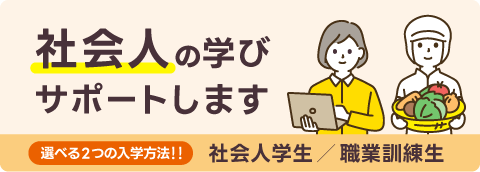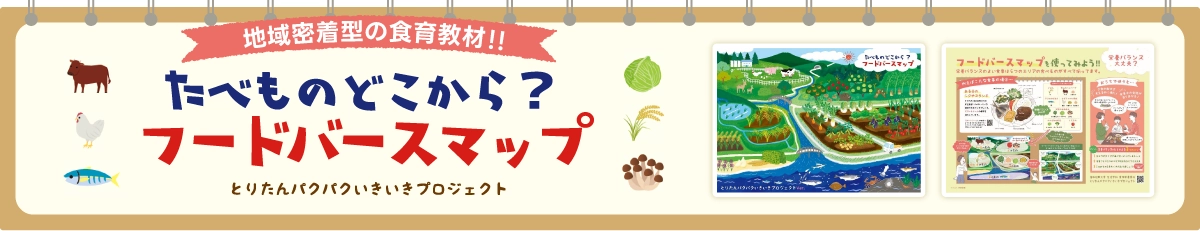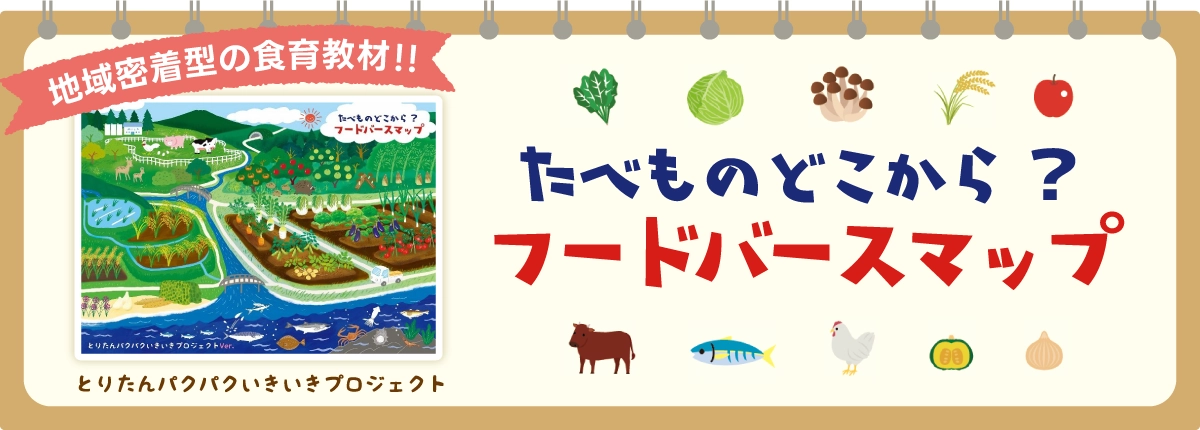生活学科 食物栄養専攻

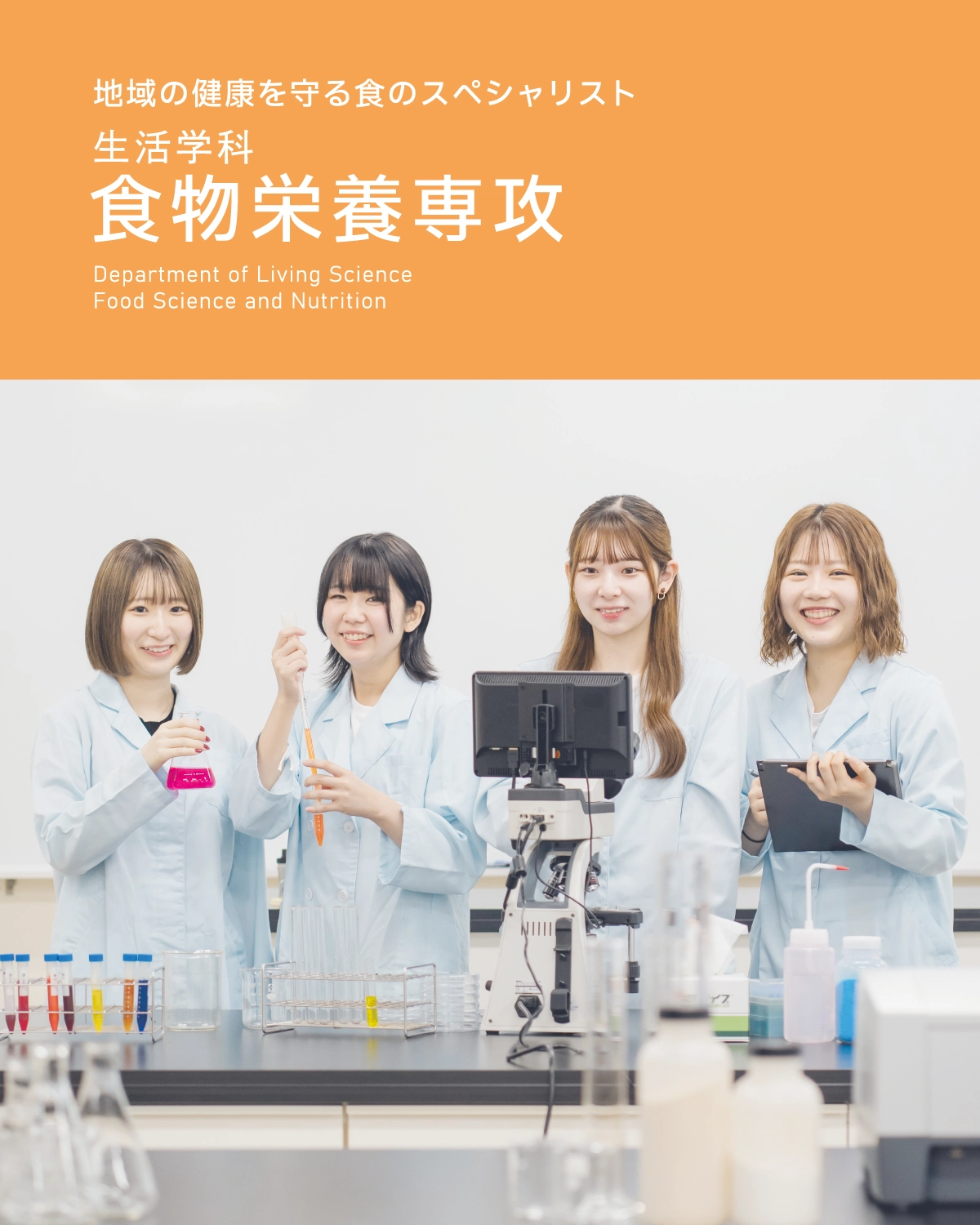
食べたものが、未来をつくる。
地域や家族の健康と笑顔を支える。
地域や家族の健康と笑顔を支える。
“食”は生きていくための基本です。
健康なカラダをつくるばかりでなく、健康なココロも育む「食育」や、病気を予防する「予防医学」の観点からも重要性が高まっています。
多くの実習や体験をとおして“食”の大切さを学び、自分の、家族の、そして地域社会の未来をつくる知識と技能をそなえた“食”のスペシャリストを養成します。
健康なカラダをつくるばかりでなく、健康なココロも育む「食育」や、病気を予防する「予防医学」の観点からも重要性が高まっています。
多くの実習や体験をとおして“食”の大切さを学び、自分の、家族の、そして地域社会の未来をつくる知識と技能をそなえた“食”のスペシャリストを養成します。

おしらせ ~ News & Topics ~
- 2025.07.07

- 2025.07.02

- 2025.06.20

- 2025.06.13

- 2025.06.12

- 2025.06.09

教員からのメッセージ
人生100年時代と食
学科長/野津 あきこ 教授
人生100年時代を迎え、長寿社会をどのように生き抜いていくのかが、問われる時代になりました。そのなかでも「食」は重要な位置づけとなっています。栄養士は健康長寿を支えていく仕事です。人間、食物、環境などの関係性に着目し、ライフステージや身体状況に応じた栄養や、食べたものが体にどのように消化吸収され、健康状態の維持・改善につながるのかを学びます。持続可能な開発目標(SDGs)にむけて一緒に学んでみませんか。

学びのポイント
地域に密着したカリキュラムで、広い知識と技能をそなえた食の専門家をめざす。

基礎から実践まで栄養士に
必要な知識と技能を習得
必要な知識と技能を習得
栄養学や衛生学などの基礎から、調理の手法や対象者に合わせた献立作成法などの現場で必要となる専門的な内容まで、幅広く学びます。


強みとなるプラスアルファの
力を身につける
力を身につける
栄養士だけでなく、栄養教諭や医療秘書実務士など、強みとなるプラスアルファの知識・資格を持った食の専門家をめざすことができます。


体験をとおして
実践力を磨く
実践力を磨く
地域イベントに参加したり、地域のプロのシェフや栄養士の方から指導を受けたりと、さまざまなかたちでの学びの機会があります。

学生インタビュー
“とりたん” で学ぶこと。
そこには、どんな出会いがあって、どんな未来が待ち受けているのでしょう?
四年制大学でもなく、専門学校でもなく、短期大学ならではの魅力とは?
ほんの少し先に、“とりたん” で学ぶことを選択し、未来へと踏み出した先輩たちの、等身大の“いま” をご紹介します。

栄養教諭の資格取得がモチベーションに。
生活学科 食物栄養専攻 2年 Aさん
入学当初から保育園の栄養士になることを目標に、視野を広げようと地域イベントやボランティア活動などにも積極的に取り組んできました。クラスの友人たちと「グルメラボ」サークルも立ち上げ、地域イベントで販売するお菓子を作ったり、地元企業とのコラボ企画を進めたりして、大変だけど充実した毎日を過ごしています。学習面では栄養教諭の資格取得という明確な目標がモチベーションとなり、意志をもって能動的に学び続けることができたことは、自分自身の成長の糧となり、自信につながっています。子どもたちに食の大切さや楽しさを伝える仕事を生涯続けるために、これからも食の知識だけではなく、人との関わりを大切に、学びを深めていきたいと思います。

体づくりと栄養を考えた食事を提供していきたい。
生活学科 食物栄養専攻 2年 Hさん
高校の部活動で体づくりをしていくなかで、食事について興味を持つようになり、栄養について学べる“とりたん” への進学を決めました。“とりたん” では「スポーツ栄養学」の授業があり、スポーツと栄養の関わりについて学びを深めるごとに、研究テーマとしての面白さを感じています。実習で特に面白かったのは、中学生対象のお弁当づくりですね。成長期に必要な栄養バランスを計算しながら、ボリュームと見た目を意識した豚のしょうが焼きをメインにした献立を考え、彩りよく仕上げることができました。卒業後は自衛官になり調理職への配属を希望しています。体をつくる栄養についてこれからも学び続けながら、おいしくて、元気の源となる食を提供し、たくさんの人に喜んでもらうことが夢です。
| 時間割 (1年次/参考) |
1限 9:00~10:30 |
2限 10:45~12:15 |
3限 13:00~14:30 |
4限 14:45~16:15 |
5限 16:30~18:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| MON | 健康科学 | ライフステージ栄養学 | 解剖生理学 | 臨床栄養学概論 | |
| TUE | 英語B | 生化学 | ヒトの科学 | ||
| WED | 給食管理 | 調理学実習 Ⅰ | |||
| THU | コミュニケーション論 | 栄養指導論実習 | 栄養学総論 | ||
| FRI | 給食管理実習Ⅰ | ||||
地域での取り組み
共同商品開発やイベント出展など、生きた学びを達成感につなげる
食物栄養専攻では「地域社会で活躍できる栄養士の育成」をめざし、地域性を取り入れた授業の実施と学生の地域活動の2点に力を入れています。授業では、地域の栄養士や食品会社の方、プロのシェフの方から、特別講師として学生に講義や実習をしていただく機会を設けています。例えば、「キャリア形成基礎」の授業では、地域で活躍している栄養士の方を招き、実際の現場での様子を聞く職業理解の機会を設けています。また、「調理学実習」では日本料理や西洋料理などのプロのシェフの方から、現場で培われた技術と理論を目と手で学ぶ機会があります。地域活動では、「くらよし国際交流フェスティバル」や「中部発! 食のパラダイスフェスタ」といった地域のイベントや、「牛乳・乳製品利用料理コンクール」などのコンクールへの積極的な参加を促しています。さらに、地域の食品会社・スーパーマーケットなどとの共同商品開発などを介して、地域の方との接点を持ち、学生の学び、達成感や満足感につながる取り組みを実施しています。

社会で活躍する先輩たち

患者さんに喜んでもらえる献立を提供していきたい
生活学科 食物栄養専攻 令和元年度卒業 Wさん

仕事のやりがいは?
行事食など、普段より大変な献立のときも職場の方がたと協力し、満足いくものが提供できたとき、やりがいを感じます。きちんと時間内に提供することへの責任を感じる経験にもなっています。患者さんが喜んでおられたと聞くとモチベーションが上がります。
とりたんの学びで得たものは?
栄養士といっても現場によってさまざまな業務がありますが、「給食管理実習」の内容はどの現場でも大切で、とても役立ちます。また地域イベントなどに参加し、いろいろな人と関わりながら、衛生面やコスト面などを考え調理し、販売したことも生かされています。
今後の目標は?
病態に応じた基準値や制限に合うような献立を考えるためには、まだまだ学ぶことがたくさんあるので、経験を重ねながら献立作成のスキルを上げていくのが目標です。また保育園や学校給食など、さまざまなライフステージの食事にも携わっていきたいですね。
[ 就職・進学実績 ]

[ 主な就職先 ]
●病院(栄養士、医療系事務) ●委託給食会社(栄養士) ●高齢者福祉施設 ●児童福祉施設 ●公務員(専門職系) ●食品関連企業(製品開発・品質管理) ●一般企業 など
[ 進学 ]
●本学 専攻科食物栄養専攻(一年制) ●四年制大学編入(島根大学生物資源科学部、くらしき作陽大学食文化学部栄養学科、美作大学生活科学部食物学科 など)